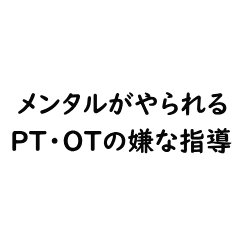 働き方
働き方 メンタルがやられる理学療法士・作業療法士の嫌な指導
今回はメンタルがやられる理学療法士・作業療法士の嫌な指導について考えてみました.
今回ご紹介したような案件はパワハラやアカハラに該当することが多いでしょう.
時代から考えればこういったハラスメントも徐々に少なくなっているのでしょうが,自分自身の指導で後輩に対して嫌な思いをさせていないかを改めて考えてみると良いですね.
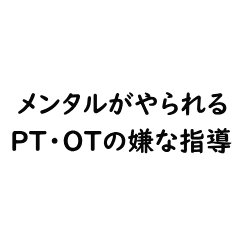 働き方
働き方 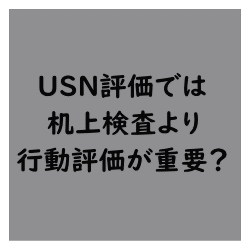 脳卒中
脳卒中 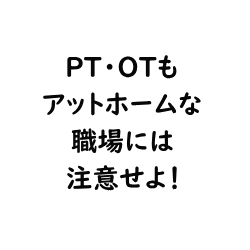 働き方
働き方 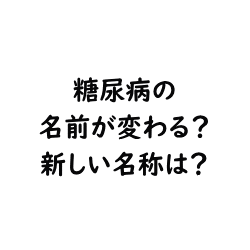 未分類
未分類 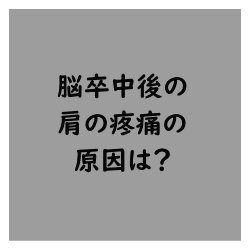 脳卒中
脳卒中  就職活動
就職活動 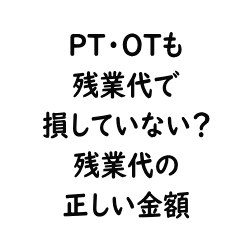 働き方
働き方 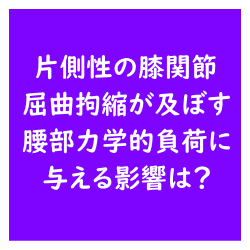 変形性膝関節症
変形性膝関節症 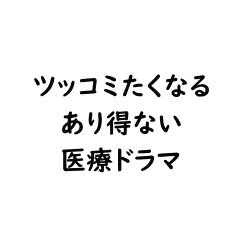 働き方
働き方 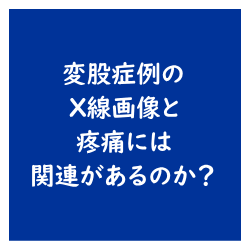 変形性股関節症
変形性股関節症 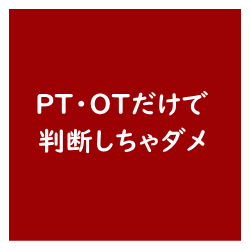 働き方
働き方 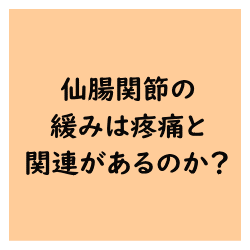 腰部
腰部 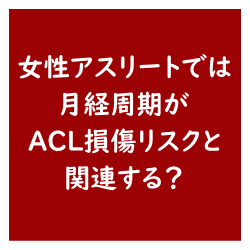 運動療法・物理療法
運動療法・物理療法 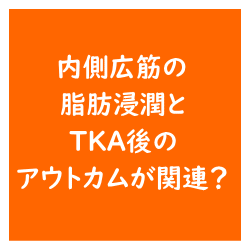 人工膝関節全置換術
人工膝関節全置換術 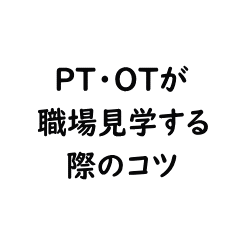 働き方
働き方 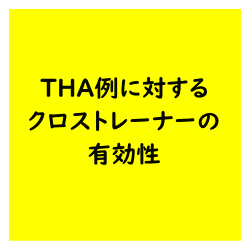 人工股関節全置換術
人工股関節全置換術 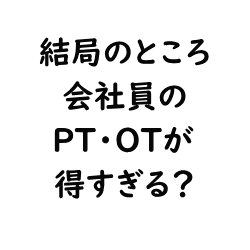 働き方
働き方 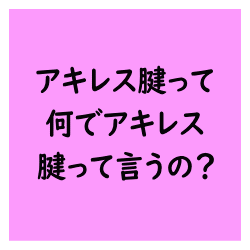 足関節周囲外傷
足関節周囲外傷 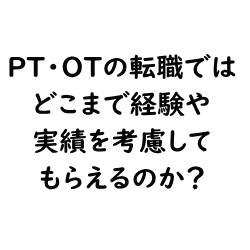 働き方
働き方  書籍紹介
書籍紹介  大腿骨近位部骨折
大腿骨近位部骨折 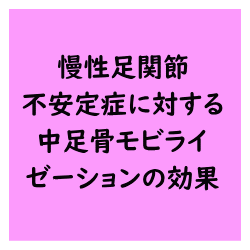 足関節周囲外傷
足関節周囲外傷  就職活動
就職活動  介護予防
介護予防  学会発表・論文投稿
学会発表・論文投稿 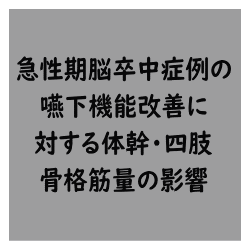 脳卒中
脳卒中 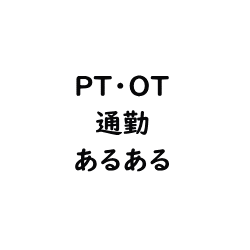 働き方
働き方 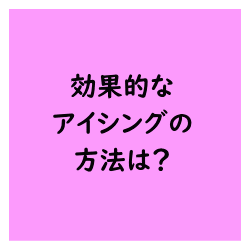 足関節周囲外傷
足関節周囲外傷 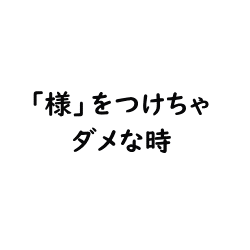 働き方
働き方 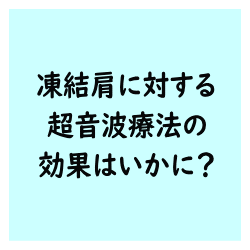 肩関節
肩関節