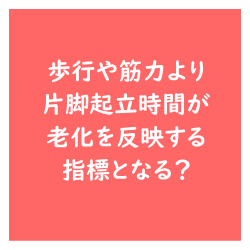 介護予防
介護予防 歩行や筋力よりも片脚起立時間が老化を反映する指標となる?
今回は歩行能力や筋力と比較して片脚起立時間が老化による運動機能低下の指標になり得るのかどうかを考えるうえで参考になる論文をご紹介させていただきました.
今回の結果から考えると歩行能力や筋力よりも片脚起立時間が運動機能低下の指標としては有用かもしれませんね.
高齢者の運動機能低下を測定するうえでは片脚起立時間の測定は必須ですね.
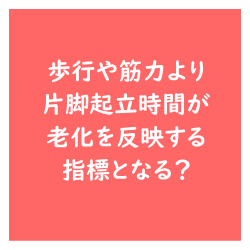 介護予防
介護予防 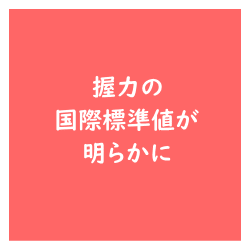 介護予防
介護予防 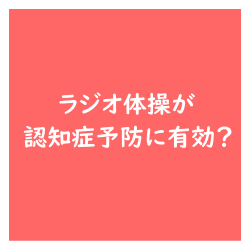 介護予防
介護予防 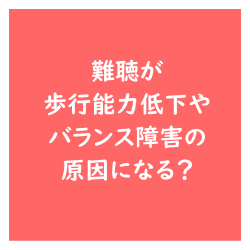 介護予防
介護予防 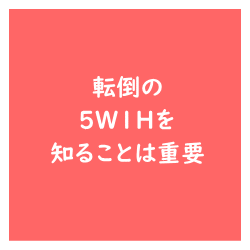 介護予防
介護予防 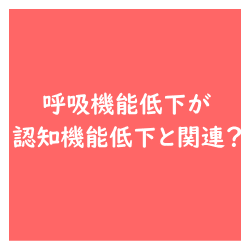 介護予防
介護予防 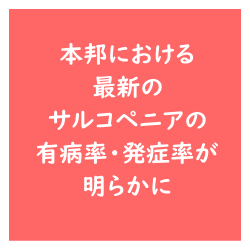 介護予防
介護予防  介護予防
介護予防 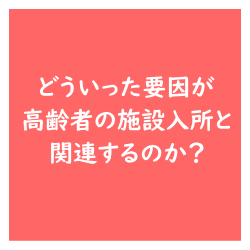 介護予防
介護予防 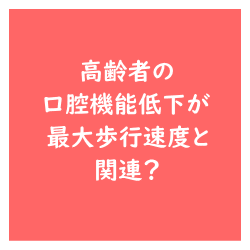 介護予防
介護予防 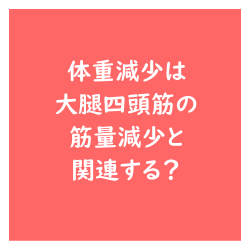 介護予防
介護予防 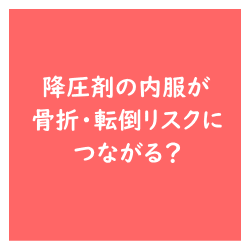 介護予防
介護予防 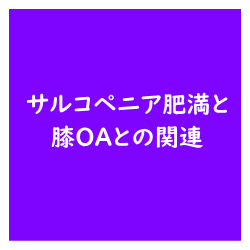 介護予防
介護予防 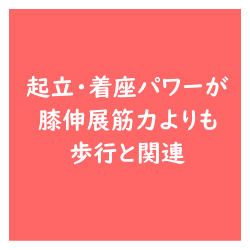 介護予防
介護予防 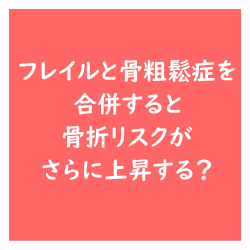 介護予防
介護予防 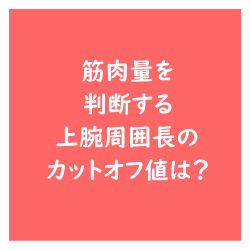 介護予防
介護予防 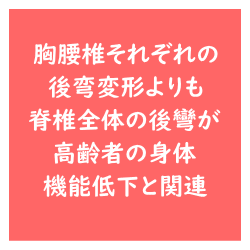 介護予防
介護予防 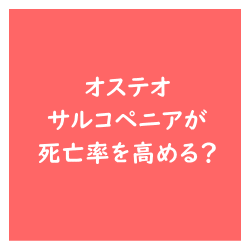 介護予防
介護予防 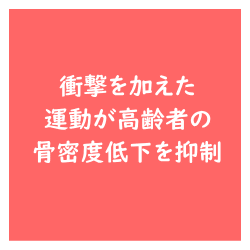 介護予防
介護予防 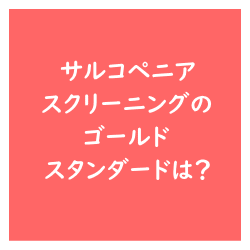 介護予防
介護予防  介護予防
介護予防  介護予防
介護予防  介護予防
介護予防  介護予防
介護予防 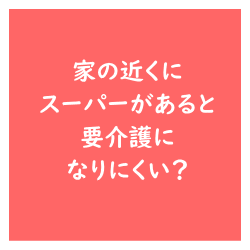 介護予防
介護予防  介護予防
介護予防 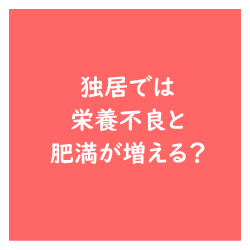 介護予防
介護予防 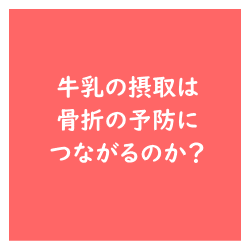 介護予防
介護予防 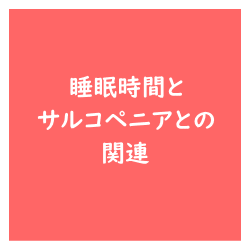 介護予防
介護予防 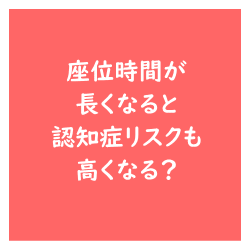 介護予防
介護予防