目次
踵骨骨折後の理学療法評価と運動療法
踵骨骨折の分類と整形外科治療については以前の記事でもご紹介いたしました.


踵骨骨折は骨折型によって整形外科的治療も異なりますので,まずは骨折型を把握することが重要となります.
踵骨骨折に対する整形外科的治療は保存療法と手術療法に大別されますが,手術療法によっても生じやすい機能低下が異なりますので,理学療法評価や運動療法を行う上でも,骨折型や手術療法の特徴を把握しておくことが重要となります.
踵骨骨折後に生じやすい疼痛
踵骨は海綿骨が主で構成されるため,偽関節は起こりにくいのですが,変形治癒や骨萎縮といった問題が生じやすい特徴があります.
そのため踵骨骨折例では,後遺症として遺残性疼痛が生じることが少なくありません.
疼痛の原因としては,①骨折に伴う距踵関節面の不適合,②狭窄性腓骨筋腱炎,③扁平足や内外反変形,④骨折そのものによる骨膜性の疼痛などが挙げられます.
特に②の腓骨筋腱に由来した疼痛は最も多く,踵骨外側の膨隆による腓骨筋腱の圧迫や,外果と外壁とによる腓骨筋腱腱鞘の狭窄による腱鞘炎が原因としてあげられます.
陥没型や粉砕骨折の場合には,踵骨外側からプレート固定を行うことが多いので,プレートを使った骨接合術を行った症例では,踵骨外側部は挿入したプレートによる体積の増加と腫脹によって,皮層・軟部組織の滑走性低下が起こりやすいので注意が必要です.
踵骨骨折後に生じやすい荷重時痛
踵骨骨折後の問題として,荷重時痛が遷延しやすいといった特徴が挙げられます.
特に残存しやすいのが踵骨外側部の疼痛です.
この踵骨外側の疼痛は整復の程度と相関があるわけではなく,長期間にわたり歩行時痛が残存するケースが少数ながら存在します.
歩行時痛の原因としては,①後距踵関節面の整復不良,②ギプス固定や長期間の免荷に伴う骨萎縮,③踵骨外側壁の膨隆に伴う狭窄性の腓骨筋腱のインビンジメントや腱鞘炎,さらに腓腹神経絞扼,④骨間距踵靱帯など距骨下関節の拘縮と足根洞症候群(足根洞部の靱帯などの軟部組織の線維化や慢性滑膜炎よる足部外側部痛)などが挙げられます.

距骨下関節にて踵骨が外反位で変形治癒した場合には,距骨下関節の固定で外側に圧が集中し,距腿関節外側のインビンジメントなどを助長する可能性があります.
一方で踵骨が内反位で変形治癒した場合には,距骨下関節の固定による外側への圧集中に加え,踵骨・距骨距骨の外側壁に荷重圧が集中する恐れがあり,荷重が足部外側に偏位してしまう可能性が考えられます.
このような荷重時痛に対しては足底板を使用して荷重時の圧を分散させるだけでも,かなり軽減が得られます.
距骨下関節にある程度の可動性があれば,内外反位での固定が直接的に距腿関節に影響を与えることは少ないわけですが,距骨下関節の内外反拘縮を呈していると,荷重痛が生じやすいわけです.
そのため早期から距骨下関節の内外反方向の可動域維持に努めることが重要であると考えられます.
踵骨骨折後の理学療法評価(関節可動域制限の特徴と可動域運動)
足関節というのは大きく分類すると,距腿関節・距骨下関節・遠位脛腓関節に分類できます.
底背屈運動に主に関わるのは距腿関節でありますので,踵骨骨折によって底背屈可動域が直接的に制限されることは少ないわけですが,踵骨骨折後に距腿関節に浮動や固定が及べば,底背屈可動域も大きく制限されるので注意が必要です.
また踵骨外側からプレート固定が行われた場合には,腓骨下端から踵骨下縁に向かう皮下の滑走性が低下しやすいので,外側軟部組織の癒着により背屈可動域が制限される場合もありますので,腓骨外果周囲組織の滑走性の評価も重要となります.
定が行われた場合は,プレートに付随する体積の増加と腫脹により皮層の滑走性が低下するため注意が必要です.
踵骨骨折例においては,距骨下関節の可動域制限が生じやすい特徴があります.
したがって内外反方向の可動域制限に注意が必要です.
前述したように内外反方向の可動性低下は荷重時の足部外側部の疼痛の原因ともなりますので,可動域獲得が重要となります.
ただし術後早期の内外反運動は骨折部の不安定性を助長することにもつながるため,内外反運動の開始時期については主治医に相談することが重要です.
Heel fat padの柔軟性評価とモビライセーション
Heel fat padは,歩行・走行時の踵部への圧緩衝系として存在し,コラーゲン線維の密性結合組織(室隔壁)から構成される小腔の中に,線維脂肪組織が満たされる蜂の巣(蜂窩)状の2重構造をしております.
これらの隔壁は足底腱膜や皮膚と強く結合し安定した状態となっています.
また,隔壁の間を血管が走行し,足底は体表で最も血管が発達した部位でもあります.
踵骨骨折は高エネルギー外傷であるため,それに伴いHeel fat padが損傷している可能性があり,柔軟性や圧痛の評価からその損傷を推察することが重要となります.
またHeel fat padの柔軟性が低下しないように,踵骨と皮膚を滑走させるようにしながら,早期から柔軟性を確保することが重要となります.
荷重の進行は?
踵骨骨折の場合は,骨折型や手術による固定性にもよりますが,4週前後の完全免荷の期間が設けられることが多いです.
比較的若年者に多い骨折ですので,部分荷重を段階的に進め6~8週で全荷重といったケースも少なくありません.
完全免荷が長期に及ぶ場合には,PTB式の装具を使って踵骨の免荷を図りながら荷重歩行を行う方法や,Graffin装具などで踵骨を免荷しショパール関節より遠位での荷重を許容して荷重歩行を進める場合が多いです.

また足底挿板を用いて踵骨へ加わる荷重を軽減する場合もあります.
いずれにしてもX線やCTで骨癒合の状況を確認しながら荷重歩行を進める必要があります.
今回は踵骨骨折に対する理学療法について考えてみました.
理学療法評価を行う場合にも,踵骨骨折に特徴的な機能障害について知っておくと良いでしょう.
また運動療法を行う上では,踵骨外側組織の癒着とHeel fat padに着目した介入が必要であります.
特に荷重時に踵骨外側に疼痛が残存する例では足底板の使用や距骨下関節の可動性改善が鍵になります.





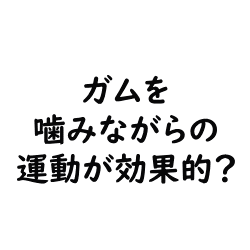

コメント