日本理学療法士協会の認定・専門理学療法士制度ができてもう少しで10年が経過しようとしておりますが,皆様はこの制度をどうお考えでしょうか?
認定・専門理学療法士資格を有する自身の経験も踏まえながら,この資格を取得すべきかどうかについて考えてみたいと思います.
目次
認定理学療法士とは
認定理学療法士とは日本理学療法士協会が新人教育ブログラム修了者を対象に,自らの専門性を高め,多回専門的臨床技能の維持,社会,職能面における理学療法の専門性を高めていくことを目的に作られた資格です.
2017年12月のデータでは全国に4055名の認定理学療法士資格を持った理学療法士がいるようです.
認定理学療法士資格を取得するためには,領域によって若干の違いはありますが,基本的には領域ごとの必須研修会と,共通科目の必須研修会を受講した上で,必要なポイントを200ポイント取得し,年度末に行われる認定理学療法士試験に合格すれば認定理学療法士を取得することができます.
領域ごとの必須研修会は領域によっては複数箇所で開催されていることもありますが,領域によっては場所が遠方の場合も少なくありません.
所属施設の立地によっては領域ごとの必須研修会,共通科目の必須研修会,試験と3度遠方へ出向く必要があり,取得に際しては交通費がけっこうかかります.
基礎(ヒト)・基礎(動物)・脳卒中・神経筋障害・脊髄障害・発達障害・運動器・切断・スポーツ・徒手・循環・呼吸・代謝・地域・健康増進・介護予防・装具・物理療法・褥瘡・疼痛管理・臨床教育・管理運営・学校教育といった23領域がありますが,領域間の格差が大きく脳卒中は取得者が800名を超えておりますが,褥創は最も少ない6名となっております.
認定理学療法士の合格率は?
気になる合格率ですが,年々厳しくなっているようです.
平成28年度の合格率は,受験者数1669名に対して,合格者数は1081名となっております.
つまり合格率は64.8%となっております.
平成29年度の合格率は,受験者数2343 名に対して,合格者数は1510 名となっております.
つまり合格率は64.4%となっております.
これは非常に低いとお考えの方が多いと思いますが,じつは試験だけの不合格ではなく,症例レポートが基準点に達しない場合や,ポイントの取得状況が十分でない場合も含まれるようです.
専門理学療法士とは? 認定理学療法士との違いは?
専門理学療法士というのは日本理学療法士協会が新人教育プログラム修了者を対象に定めた資格で,一定の臨床における専門性を高めること,良質なサービスを提供する能力を備えること,そして理学療法の学問的発展に貢献出来る研究能力を高めていくことを目的とした資格です.
認定理学療法士が職能に基づく臨床的要素の強い資格であるのに対して,専門理学療法士は学術的要素がメインとなる資格と言えるでしょう.
これまでは専門理学療法士資格は認定理学療法士の上位資格と考えられてきましたが資格の2020年7月に並列性が公表されております..
2016年4月の理学療法士協会のデータによると,総会員数96,648名に対して専門理学療法士を取得したのは1,792名となっております.
基礎・神経・運動器・内部障害・生活環境支援・教育・物理療法といった7専門領域がありますが,これも分野ごとの格差が大きく運動器での取得が604名と頭一つ抜けて多いのに対し,物理療法は63名とかなり少ないような状況です.
専門領域を1つ以上選択してポイントを集めて申請するという大まかな流れは認定理学療法士と同じですが,専門理学療法士の場合には必須研修会の受講や試験の受験は必要がありません.
申請条件としては,新人教育プログラムを修了している,専門領域を登録してから5年以上が経過している,各領域にて設定された履修ポイントを560ポイント取得しているといった条件が挙げられます.
またすでに認定理学療法士の資格を取得している場合,選択した専門領域が同じであれば380ポイントの取得で専門理学療法士になることが出来ます.認定理学療法士資格の取得によって臨床実践ポイント180ポイントが加算されるためです.申請に必要な560ポイントの内訳は,以下のようになっています.
1.学術ポイント:200ポイント
研究に関する業績や,学術の発展に寄与する業績によって獲得することが出来ます.学会参加だけでも100ポイントが認められ,必修論文も40~80ポイントと大きい配分となっています.査読のある雑誌に筆頭論文が掲載されることが条件であり,これが慣れない方にとっては取得に当たっての1つ目の山であったりします.
2.教育ポイント:100ポイント
指導的な働きかけや,後輩の育成に寄与する業績によって獲得出来ます.
臨床実習指導者の経験があれば40ポイントは認められますが,残りの60ポイントは論文や学会発表,講習会の講師などの活動で取得しなければなりません.
特に講習会などは規定によって安易に開催できるものではないため,一人で取得するのが難しいポイントとなっています.実は先の学術ポイントにおけるポイント取得よりも難しいのが教育ポイントです.
教育ポイントは県士会や協会主催の研修会のようなOfficialな研修でないと付与が認められておりません.
一方で新人教育プログラムや県士会での小さな研修会であっても県士会主催のものであれば講師ポイントが認められます.
県士会関連の講師をするには,県士会活動に日頃から関わっておくことも重要だと思います.
また県によっても教育ポイントの取得しやすさには差があったりします.
会員数の多い都会ではなかなか県士会での講師を務める機会も少ないようで,教育ポイントの取得が最難関であったりします.
3.分野別選択ポイント:80ポイント
各専門分野が個別に指定した業績によって取得出来ます.
各分野で開催されている必須発表会に参加することで認められます.これは最も取得しやすいでしょう.
4.臨床実践ポイント:180ポイント
認定理学療法士の資格を持っている,もしくはそれと同等の業績を残すことで取得出来ます.
専門領域が同じであれば認定理学療法士の資格を持っているだけでクリア出来るポイントです.
そのほかには学会参加や論文発表でも獲得出来るようになっています.
このポイントについても取得しやすいポイントだといえるでしょう.
ポイント基準については以下をご参照ください
認定・専門理学療法士ポイント基準
認定・専門理学療法士の金銭的インセンティブの現状は?
現状では認定・専門理学療法士ともに,待遇面で有利になることはほぼないと考えてよいと思います.
日本理学療法士協会はま広告ガイドラインへの掲載に向け,活動を進めておりますが,診療報酬上に反映されるという可能性は非常に低いと思います.
今のところ認定・専門理学療法士資格を持っていると講習会で講師を務めた際に,謝金が高くなる(専門理学療法士を持っていると技師長と同格となる)といった場合もありますが私が金銭的インセンティブと感じるのはそのくらいでしょうか.
これもあくまで協会が開催する一部の研修会ですのであまり魅力のあるものではありませんが…
認定・専門理学療法士取得をするメリット,給料上がる?
前述したように現在のところ認定・専門理学療法士を取得することによる金銭的インセンティブはほぼ無いと考えてよいと思います.
認定・専門理学療法士資格を持つ身として,認定・専門理学療法士資格を持っているとどういった利益があるかをご説明いたしますと,一番は資格取得によって自身を生涯学習する環境に追い込むことができるといったことでしょうか.
認定・専門理学療法士資格を持っていると,学会演題の査読や座長の仕事を依頼されることが多いです.査読や座長の機会を与えられれば嫌でも学習するわけです.
また認定・専門理学療法士資格は5年に1回更新する必要がありますので,更新に向けて論文を書いたり,研修会や学会に参加する必要があります.
すなわち認定・専門理学療法士資格を持つと勉強をし続ける環境に自分を追い込むことができるといった利点があります.これを利点と考えられるかどうかは人それぞれだと思いますが,職業人として学び続けるためには何かしらの理由も必要かもしれません.
将来的な認定・専門理学療法士のインセンティブ(2019/1/6)
2019年1月にPOSTのインタビュー記事の中で日本理学療法士協会会長の半田一登氏がこんなコメントをされております.
「今,協会として何をしようとしているかというと,認定・専門理学療法士をとるために何らかの努力をしている人たちを,診療報酬の形としてメリットをつけましょうよ,という交渉をしています.」
「これは例えですが,簡単に説明すると,脳血管疾患は今200点です.それに対して,脳血管疾患の特別な勉強を行なって,ライセンスを取得した場合210点.その逆にそれを持っていない人たちが行うと190点.トータルの診療報酬で考えると今までと一緒ですよ」
「ですから,リハの医療費総額が増えるわけではありません.当然,努力した人としていない人の賃金差は,あって然るべきことじゃないですか.」
これは現状の医療費総額が増えるわけでもない現状を考えても実現が可能なもしれないと思える考想です.
日本理学療法士協会のこの構想がどこまで実現できるかはわかりませんが,やはり大きいのは政治力(次回の選挙も含めて)と医師会・看護協会をどう説得するかというところだと思います.
診療報酬が変われば金銭的なインセンティブにも差が生まれる可能性が高くなりますので,早めに認定・専門理学療法士を取得するとともに,今後も日本理学療法士協会の動きに注目しておく必要があると思います.
リハビリ業界では,年々理学療法士が増加していることにより,理学療法士の価値が相対的に下がってきてしまっている状況があります.
現状では資格取得による金銭的インセンティブはほぼ皆無に近いですが,今後は資格の価値も変化する可能性があります.ここで周囲に差を付ける資格を取得しておけば,リハビリ職の需要が高まる2025年に向けて,必要とされる理学療法士になれる可能性もあります.
皆様もこの記事を機会に取得してみてはいかがでしょうか.
認定・専門理学療法士の更新に関しても記事を作成しておりますので以下の記事もご参照ください

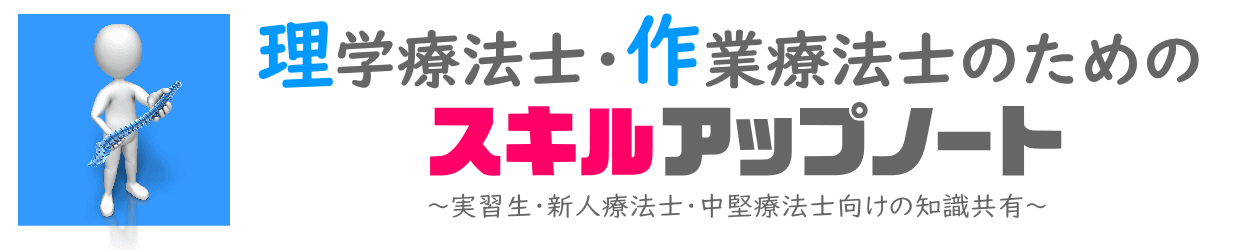




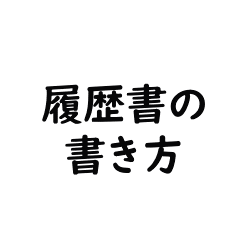

コメント
[…] 認定理学療法士・専門理学療法士って取得すべき?合格率は? 診療報酬への影響は?日本理学療法士協会の認定・専門理学療法士制度ができてもう少しで10年が経過しようとしており […]
[…] 認定理学療法士・専門理学療法士って取得すべき?合格率は? 診療報酬への影響は?日本理学療法士協会の認定・専門理学療法士制度ができてもう少しで10年が経過しようとしており […]