前回は高齢者の転倒の原因についてご紹介いたしました.

転倒の原因は様々ですが,加齢変化による運動機能低下,身体的疾患,薬物,物的環境が大切です.
中でも運動機能低下は運動を行うことで改善が得られることが多いので,転倒予防を図る上では適切な運動を行って運動機能を向上させることが重要です.
目次
転倒の原因は身体機能レベルによって異なる
転倒予防を目的として運動を行う場合には,前回ご紹介した「筋力」・「バランス能力」・「歩行能力」を改善することが重要となります.
一方でこれら「筋力」・「バランス能力」・「歩行能力」といった機能が比較的良好であるにもかかわらず転倒してしまう人が数多く存在するということが最近の研究でわかってきました.
つまり元気高齢者の場合には,「筋力」・「バランス能力」・「歩行能力」が良好にもかかわらず転倒してしまうのです.
では元気高齢者はなぜ転倒するのでしょうか?

上の表はTimed up and go testの結果によって4群に分け,各群の中でさらに転倒群と非転倒群に分類した上で,運動機能を比較したものです.
Slowest(TUGがかなり遅い群)
非転倒群に比較して転倒群の筋力が有意に低い(立ち上がりに要する時間が有意に長い)
Slower(TUGが遅い群)
非転倒群に比較して転倒群の筋力が有意に低い(立ち上がりに要する時間が有意に長い)
Faster(TUGが速い群)
筋力には差は無く,非転倒群に比較して転倒群で二重課題(認知課題)の成績が不良である
Fastest(TUGがかなり速い群)
筋力には差は無く,非転倒群に比較して転倒群で二重課題(運動課題)の成績が不良である
少しわかりにくいかもしれませんが,簡単に言うとTUGの遅い方は転倒群・非転倒群間で筋力に差があり,TUGの速い方は転倒群・非転倒群の間で筋力に差が無い一方で二重課題処理能力に差があるといった結果です.
つまり元気高齢者は二重課題処理能力が低下しているために転倒されている方が多いということです.
転倒予防における二重課題処理能力とは?
では二重課題処理能力とは何でしょうか?
二重課題処理能力というのは2つ以上のことを同時に行う能力のことを指します.
Duak-task(デュアルタスク)能力とも呼ばれますが,われわれの日常生活を考えた際には,ただただ歩くということは少ないですよね?
話しながら歩いたり,考えながら歩いたり,電話をしながら歩いたり,コップに入った水をこぼさないように歩いたりと複数の課題をわれわれは同時に処理しているのです.
歩行補助具を使用していない移動能力の高い高齢者も5人に1人は1年間に1回以上は転倒しており,この転倒の原因が二重課題処理能力の低下に起因するものなのです.
特にこんな方は注意が必要です.
- 歩きながら話をしている時につい立ち止まってしまう
- テレビを見ながら皿洗いをしていると,皿洗いの手が止まってしまう
- スーパーを歩きながら献立を考えることができない
ですので転倒予防介入を行う場合には,一律に筋力トレーニングを実施すればよいということではなくて,身体機能をきちんと評価した上で虚弱な方には筋力トレーニングを,元気な方には二重課題処理能力を向上させるようなトレーニングを実施する必要があります.
次回は具体的な二重課題トレーニングについて紹介させていただきます.

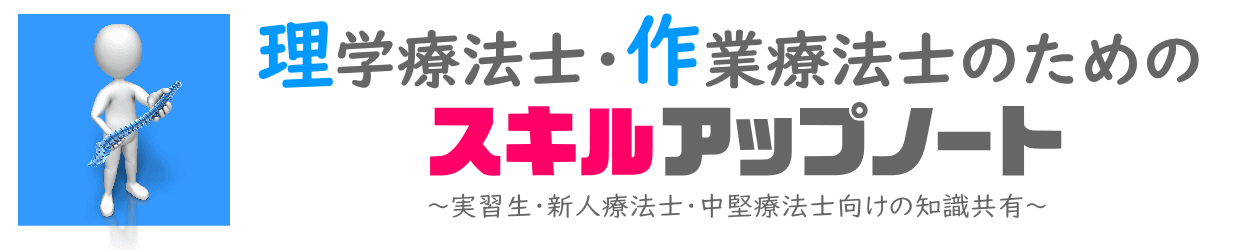




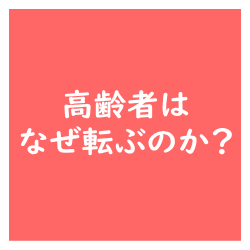

コメント