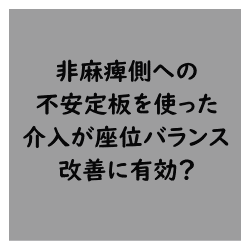 脳卒中
脳卒中 脳卒中症例に対する非麻痺側への不安定板を使った介入が座位バランス改善に有効?
今回は脳卒中症例に対する非麻痺側への不安定板を使った介入が座位バランス改善に有効性を考えるうえで参考になる論文をご紹介させていただきました.
今回の結果から考えると非麻痺側への介入はバランス能力改善に有効だと考えられますね.
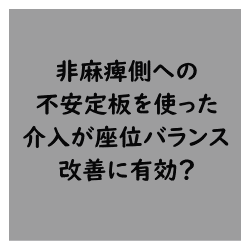 脳卒中
脳卒中 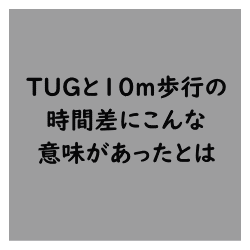 脳卒中
脳卒中 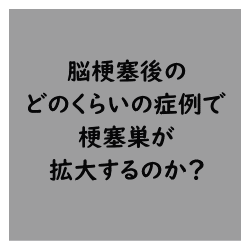 脳卒中
脳卒中 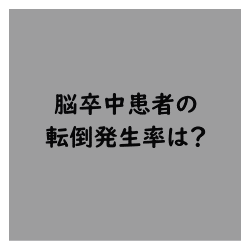 脳卒中
脳卒中 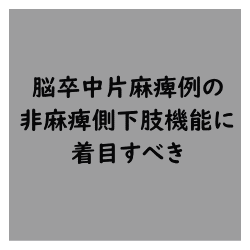 脳卒中
脳卒中 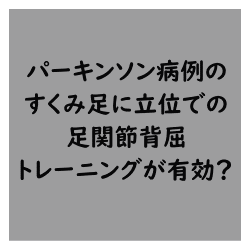 脳卒中
脳卒中 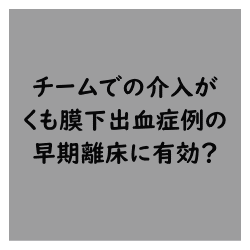 脳卒中
脳卒中 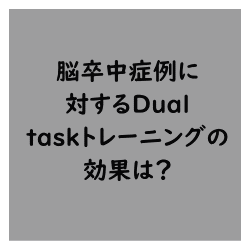 脳卒中
脳卒中 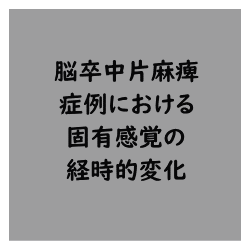 脳卒中
脳卒中 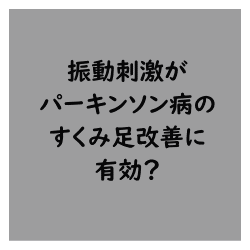 脳卒中
脳卒中 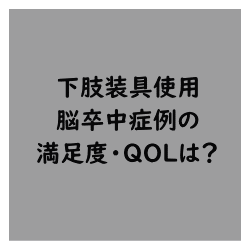 脳卒中
脳卒中 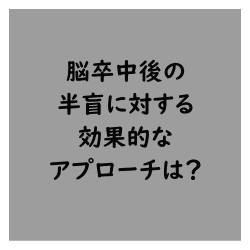 脳卒中
脳卒中 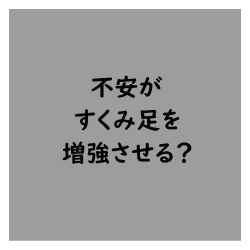 脳卒中
脳卒中 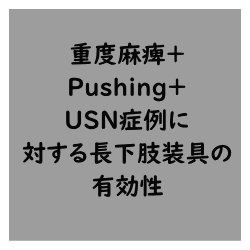 脳卒中
脳卒中 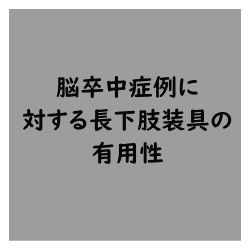 脳卒中
脳卒中 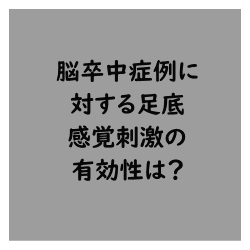 脳卒中
脳卒中 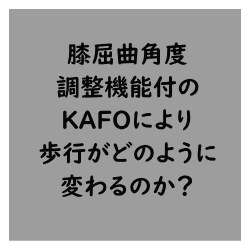 脳卒中
脳卒中  脳卒中
脳卒中 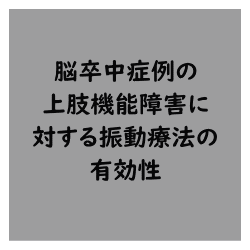 脳卒中
脳卒中 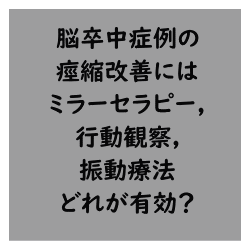 脳卒中
脳卒中 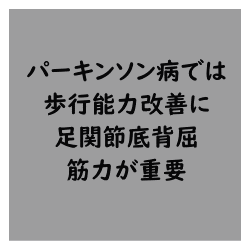 脳卒中
脳卒中 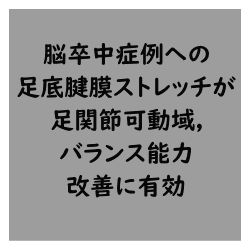 脳卒中
脳卒中 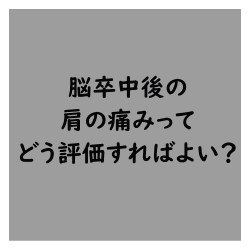 脳卒中
脳卒中 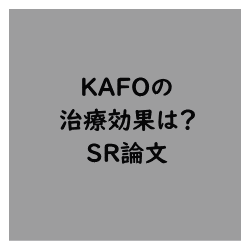 脳卒中
脳卒中 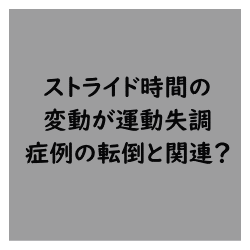 脳卒中
脳卒中 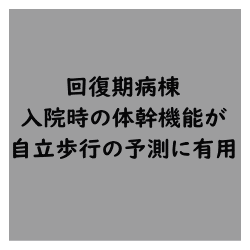 脳卒中
脳卒中 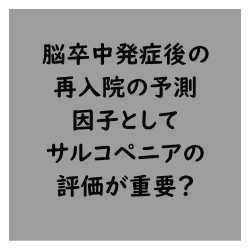 脳卒中
脳卒中 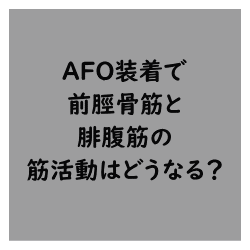 脳卒中
脳卒中 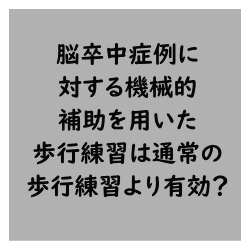 脳卒中
脳卒中 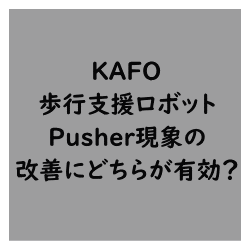 脳卒中
脳卒中