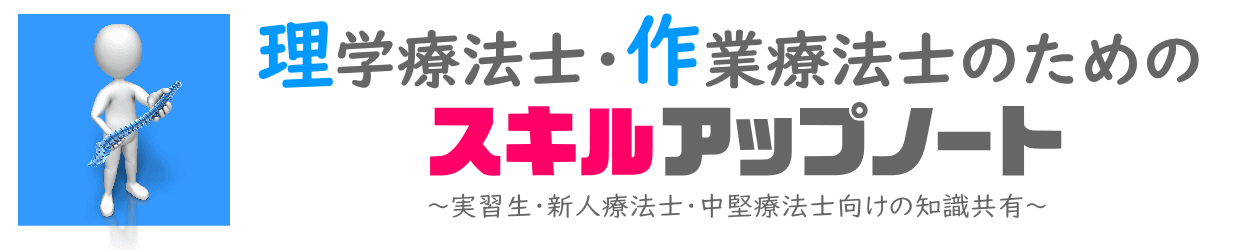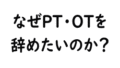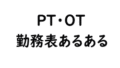目次
認知症があるから理学療法の対象にならない?
理学療法士であればカンファレンスなんかでよく耳にしませんか?
「Aさんは認知症があるからなかなかリハビリが進みません」
「Bさんは認知症があるから在宅復帰は難しいと思います」
「Cさんは認知症があるからリハビリの対象にはなりません」
確かに認知症に伴うさまざまな症状がリハビリテーションの妨げになることは少なくないと思いますし,在宅復帰にあたっては認知症に伴う様々な症状を考慮した上での介護保険サービスの提供やご家族への指導が必要となります.
ただ認知症があるからリハビリの対象にならないといった考え方はどうでしょうか?
今回は認知症があるから理学療法の対象にならないといった考え方について考えてみたいと思います.

認知症があるから理学療法の対象にならない?
認知症に伴う中核症状や周辺症状というのはリハビリテーション遂行の妨げになることは多いと思います.
でも認知症があるから理学療法の対象にならないというのはどうなのでしょうか?
じゃあ疼痛が強いクライアントがいた場合に,疼痛が強いから理学療法の対象にならないなんて考え方を理学療法士がするでしょうか?
おそらく疼痛が強ければ,疼痛を評価して,何かしらの対処をしますよね.
認知症の場合も同様だと思います,中核症状である短期記憶の評価をしたり,周辺症状の評価をしたりということが基本になると思います.
しっかりとした評価を行ったうえでどう対処するべきかを考えるのが理学療法士の仕事ですよね.
それを認知症があるから理学療法の対象にならないで片づけてしまうのはいかがなものでしょうか?
30年くらい前までは…
確かに30年くらい前までは認知症を合併されている高齢者も少なかったので,認知症はリハビリテーションの阻害因子として位置づけられてきたところがあります.
ただ今はどうでしょうか?
むしろ80歳以上の高齢者では認知症を合併しているのが当たり前になってきているのが現状だと思います.
むしろ高齢の方だと認知症を合併していないクライアントを探すのが難しいくらいだと思います.
認知症を合併しているから理学療法の対象にならないなんて言ってたら仕事無くなっちゃいますよね.
身体活動が認知機能に与える影響
また昨今は身体活動が認知機能に与える影響に関してわれわれが提供する理学療法を支持するエビデンスも多く出てきております.
むしろ認知症を合併しているからこそ,理学療法をという時代になりつつあるわけです.
認知症を合併しているから理学療法の対象にはならないではなく,認知症を合併しているからこそ理学療法が必要なわけです.
本邦では認知症高齢者の割合が年々増加しているにもかかわらず,認知症例に対する理学療法というのは専門分野としてあまり確立されていないのも実際だと思います.
生活動作に関連付けたマネジメントが必要
そうはいっても実際に認知症を合併した症例に理学療法を提供するというのは簡単なことではありません.
理解力が低下した認知症例の場合には,細かい運動の指示入力は難しいことが多いですし,周辺症状が強い場合には暴言や暴力などの行為や理学療法を拒否されるといった場合もあると思います.
いずれにしても認知症例を対象とする場合には生活動作に関連付けたマネジメントが必要だと思います.
動作の中で運動を組み立てる視点が持てれば,うまく介入できることも少なくありません.
機能ばかりに目を向けていると認知症を合併しているクライアントは理学療法の対象にならないなんて考えに至ってしまいますよね.
今回は認知症があるから理学療法の対象にならないといった考え方について考えてみました.
認知症を合併しているから理学療法の対象にはならないではなく,認知症を合併しているからこそ理学療法が必要なわけですね.
今後もう少し認知症例に対する理学療法の専門性が確立されていくことを切に願います.