前回までは高齢者の転倒予防におけるバランストレーニングの重要性,バランス機能評価の重要性についてご紹介いたしました.

そもそも「バランス」って何でしょうか?今回は「バランス」を支持基底面と重心位置との関連から代表的なバランス評価と絡めながら考えてみたいと思います.
目次
リハビリ(理学療法)におけるバランス機能の定義
内山靖先生
「バランスとは, 重力をはじめとする環境に対する生体の情報処理機能の帰結・現象で平衡にかかわる神経機構, 骨アライメント, 関節機能, 筋力などの要素により支持基底面に重心を投影する能力である」
望月久先生
「バランスとは姿勢調節における安定性に着目した概念で, 支持基底面内に重心線を収めることが要件となり, 筋力, 関節可動域, 呼吸循環機能など多くの身体機能によって達成されるものである」
お2人の先生の定義に共通するのは支持基底面と重心の関係からバランスを捉えようとしているところです.
理学療法士であればやはり支持基底面と重心位置(正確には足圧中心位置)との関係からバランスを捉えるのがスタンダードだと思います.
リハビリ(理学療法)におけるバランス機能の階層構造
また島田先生が2006年にバランス機能を階層的に捉える方法を考案されております.

この階層構造ではバランス機能を4段階の因子構造でとらえることとなっております.
因子1:静的姿勢保持
因子1は支持基底面内で重心を保持する能力です.片脚立ち(One leg standing:OLS)やtandem standingなどがこれに該当しますが,小脳性の失調のある方などは重心を中央にとどめておくことが難しい方が多く,この因子1が苦手だったりします.
因子2:外乱負荷応答
因子2は外乱負荷に抵抗しながら支持基底面内で重心を保持する能力です.
この因子2に関してはMajorなテストが存在しませんが,Manual Pertubation testと呼ばれる徒手にて外乱負荷を加えてその際のバランス反応を診る検査などがこれに該当します.
因子3:随意運動中のバランス(支持基底面固定)
因子3は支持基底面内で重心を移動させる能力です.
因子3に関してはFunctional Reach(FR)が代表的ですが,パーキンソン病の方が苦手な能力になります.Lateral reach等もこの因子2に含まれます.
因子4:随意運動中のバランス(支持基底面移動)
因子4は支持基底面を移動させながら重心を支持基底面の中央に保持する能力です.Timed up and Go testやtandem gait等が因子4に含まれます.
このようにバランスと一言で言ってもいろんな能力が含まれていることがわかると思います.
また理学療法士はバランス評価がそれぞれどういったバランス要素を評価するものであるのかを知っておくことが重要です.
実はバランスをこのように階層構造でとらえることができれば,どのようなバランストレーニングを行った方が良いかといった介入方法にも活かすことができます.
バランス機能の特異性
そうはいってもバランスが悪い人は因子1~4まで全てが不良で,バランスが良い人は因子1~4まで全てが良好なので階層構造を使ってバランスを捉える必要がないのではないかとお思いの方もおられるかもしれません.
実はバランスには特異性があることがわかっています.
つまり動的バランスが不良であっても静的バランスが良好な方もいれば,その逆もあり得るということです.
また虚弱高齢者(n=34)をControl group(n=10), Static Balance Ex group(n=12), Dynamic Balance Ex group(n=12)の3群に分類して実施された無作為化比較試験によると,動的バランストレーニングを行った群は動的バランス能力のみに改善が得られ(静的バランスには変化なし),静的バランストレーニングを行った群は静的バランス能力のみに改善が得られております(動的バランスには変化なし).
こういった結果を見るとバランスを階層構造で評価して適切なトレーニングを実施することが重要であると考えられます.
今回はバランス機能の捉え方について紹介させていただきました.次回は代表的なバランス評価について,その利点・欠点について考えてみたいと思います.
参考文献
1)内山靖, 姿勢調節の理学療法, 2004
2)望月久: バランス. 理学療法ジャーナル35: 373, 2002
3)島田裕之, 他: 姿勢バランス機能の因子構造 臨床的バランス機能検査による検討. 理学療法学33: 283-288, 2006
4)Hiroyuki S, et al: Specific effects of balance and gait exercises on physical function among the frail elderly. Clin Rehabil17: 472-479, 2003
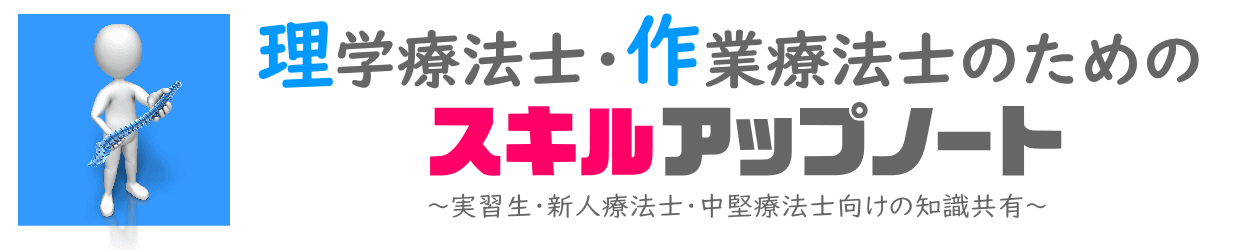




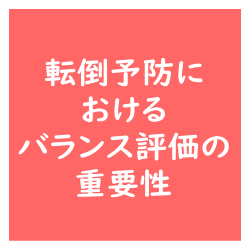
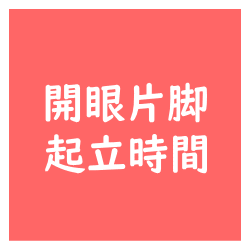
コメント