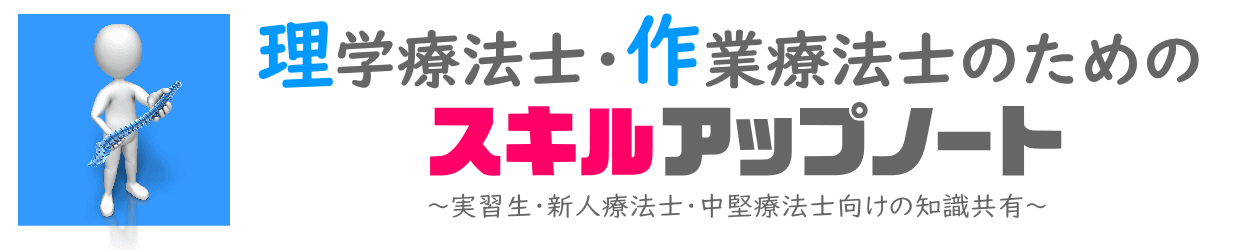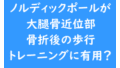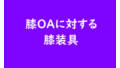目次
脳卒中症例における固有感覚の重要性
脳卒中症例では運動障害が問題視されることが多いです.
しかしながら運動障害とともに重要となるのが感覚障害です.
今回は脳卒中症例における固有感覚障害の問題を考えるうえで参考になる論文をご紹介させていただきます.

今回ご紹介する論文
Front Neurol. 2025 Jan 6:15:1407297. doi: 10.3389/fneur.2024.1407297. eCollection 2024.
Ankle joint position sense acuity differences among stroke survivors at three walking ability levels: a cross-sectional study
Jinyao Xu 1, Jeremy Witchalls # 1, Elisabeth Preston 2, Li Pan 3, Gengyuan Zhang 4, Gordon Waddington 1, Roger David Adams 1, Jia Han # 5
Affiliations Expand
PMID: 39835142 PMCID: PMC11743361 DOI: 10.3389/fneur.2024.1407297
今回ご紹介する論文は2025年に掲載された論文です.
研究の背景
Background: Despite the importance of lower limb sensation in walking highlighted in systematic reviews, there is limited research investigating the effect of proprioceptive deficits after stroke and any relationship with walking ability.
システマティックレビューでは歩行における下肢感覚の重要性が強調されているにもかかわらず,脳卒中後の固有感覚障害の影響や歩行能力との関係を調査した研究は限られております.
研究の目的
Objectives: With stroke survivors of different walking ability, this study aimed to (1) explore side (affected/unaffected) and movement direction (inversion/plantar flexion) effects in ankle joint position sense (JPS) acuity, and (2) compare ankle JPS acuity between groups of stroke survivors with different walking ability.
この研究では歩行能力の異なる脳卒中生存者を対象として
(1)足関節位置感覚(JPS)鋭敏性における側方(患側/非患側)および運動方向(倒立/底屈)の影響を検討し,(2)歩行能力の異なる脳卒中生存者グループ間で足関節位置感覚を比較することを目的としております.
研究の方法
Methods: Seventy subacute stroke survivors were recruited and divided into three groups based on walking ability, as determined by their gait speed on the 10-Meter Walking Test: household (<0.4 m/s), limited community (0.4-0.8 m/s) and community (>0.8 m/s). Ankle JPS acuity was measured by the active movement extent discrimination apparatus (AMEDA).
70例の亜急性期脳卒中生存者を対象として,10m歩行テストにおける歩行速度によって決定される歩行能力に基づいて,家庭(0.4m/s未満),限定的地域(0.4~0.8m/s),地域(0.8m/s以上)の3群に分類しております.
足関節位置覚は能動的運動範囲識別装置(AMEDA)を用いて測定しております.
研究の結果
Results: A significant difference was found between sides, with the AMEDA scores for the unaffected side significantly higher than for the affected side (F1.67 = 22.508, p < 0.001). The mean AMEDA scores for plantar flexion were significantly higher than for inversion (F1.67 = 21.366, p < 0.001). There was a significant linear increase in ankle JPS acuity with increasing walking ability among stroke survivors (F1.67 = 17.802, p < 0.001).
左右間に有意差が認められ,非罹患側のAMEDAスコアは罹患側より有意に高い結果でありました(F1.67=22.508、p<0.001).
足底屈の平均AMEDAスコアは回内よりも有意に高い結果でありました(F1.67=21.366、p<0.001).
脳卒中生存者では歩行能力の改善に伴い足関節位置感覚が有意に直線的に増加しました(F1.67 = 17.802, p < 0.001).
研究の結論
Conclusion: After stroke, ankle JPS acuity on the affected side was lower than the unaffected side. Stroke survivors had higher ankle JPS acuity in plantar-flexion movements, compared with inversion movements. Overall, stroke survivors with higher ankle JPS acuity tended to have higher walking ability, highlighting the importance of ankle JPS acuity in walking ability after stroke. These findings provide new insights into proprioceptive deficits after stroke and their relevance in neurorehabilitation.
脳卒中後,麻痺側の足関節位置感覚は非麻痺側よりも低い結果でありました.
脳卒中生存者の足関節位置感覚は倒立運動と比較して,足底屈運動で高い結果でありました.
全体として足関節位置感覚が高い脳卒中生存者は歩行能力が高い傾向にあり,脳卒中後の歩行能力における足関節位置感覚の重要性が強調されました.
これらの知見は脳卒中後の固有受容障害に関する新たな知見と神経リハビリテーションにおけるその関連性を提供するものであります.
今回は脳卒中症例における固有感覚障害の問題を考えるうえで参考になる論文をご紹介させていただきました.
今回の結果から考えると位置覚というのは歩行能力改善に重要であることが改めてうかがえます.
位置覚改善を目的とした理学療法を確立する必要がありますね.