前回は大腿骨骨幹部骨折例に対する手術療法についてご紹介いたしました.
今回は大腿骨骨幹部骨折例における理学療法評価について,骨折や手術の特徴を鑑みながら考えてみたいと思います.
目次
大腿骨骨幹部骨折例に対する理学療法評価
1.視診・触診
急性期には体表から明らかな骨折部周囲の腫張を確認することができます.
大腿骨は人体で最長の長管骨ですので,骨折部位と腫張が起こっている部位を照らし合わせて確認することが重要です.
Interlocking Nailを使用した骨接合術では外固定が使用されることは少ないですが,受傷側下肢の免荷が必要な場合には,大腿筋群・下腿筋群の筋萎縮が起こりやすいので,筋腹の大きさを視診で確認するとよいでしょう.
2.疼痛の評価
大腿骨骨幹部骨折に限ったことではありませんが,安静時および動作時の疼痛について,疼痛の部位や性質を確認しましょう.
疼痛の強さについてはVAS(Visual Analogue Scale)やNRS(Numerical Rating Scale)等が用いられることが多いです.
大腿骨骨幹部骨折では中間広筋の損傷を合併しやすいので,特に膝関節屈曲に伴う疼痛が強い症例が多いです.他動運動時に限らず,起き上がりや立ち上がりなどの際に膝関節の屈曲が強制される動作で疼痛が出現しやすいので,動作時の疼痛についても評価しておく必要があります.
極める大腿骨骨折の理学療法 医師と理学療法士の協働による術式別アプローチ/斉藤秀之/加藤浩
3.形態測定
骨幹部骨折に伴う腫張や出血によって,大腿部から膝関節にかけて腫張・浮腫を伴うことが多いため,周径を継続的に評価する必要があります.
また粉砕骨折で整復が不十分であった症例や,Dynamizationが行われた症例の場合には,大腿骨が短縮しますので,大腿長や転子果長といった下肢長を確認することも重要となります.
4.感覚検査
頻度としては多くありませんが,大腿神経や坐骨神経が損傷を受けている可能性がありますので,大腿神経領域・坐骨神経領域の感覚検査を確認程度に行っておくとよいでしょう.
5.関節可動域測定
大腿骨骨幹部骨折といえば膝関節の屈曲可動域制限というほど膝関節屈曲可動域制限が生じやすいです.
また術式によっても可動域制限の原因が異なる場合があります.
順行性髄内釘が使用された場合は大腿骨遠位部に横止めスクリュー(Distal locking screw)が経皮的に挿入されるため,皮膚は当然ながら外側広筋にも侵襲が加わりますので,膝関節屈曲可動域制限が出現しやすくなります.
逆行性髄内釘が用いられた場合には,順行性髄内釘と同様に横止めスクリューの影響に加えて,髄内釘の挿入部である膝蓋靱帯や膝蓋支帯,膝蓋下脂肪体の癒着や瘢痕化が起こりやすい点に注意が必要です.
プレート固定が行われた場合は,骨折部を露出するために腸脛靱帯・大腿筋膜と外側広筋は広く展開されるため,膝関節屈曲可動域制限や股関節内転可動域制限が出現しやすくなります.
加えて大腿骨骨幹部骨折は高エネルギー外傷が多いので,骨折の影響のみならず受傷時の軟部組織損傷にも留意する必要があります.
したがって手術侵襲に伴う組織の短縮のみならず,股関節内転筋群やハムストリングスといった大腿部の筋群の損傷・短縮が膝関節屈曲可動域制限の原因となることもあります.
6.筋力評価
前述したとおり大腿骨骨幹部骨折には中間広筋の損傷を合併しやすいといった特徴がありますので,膝関節伸展筋力が低下しやすい特徴があります.
特に広筋群の機能低下が出現しやすいので, extension lagが出現しやすいのも特徴的です.したがって通常の筋力検査に加え,extension lagの有無とその伸展不全の角度を評価します.
順行性髄内釘が使用された場合は,大腿骨転子部骨折に対する骨接合術(γ-nail)と同様に,中殿筋や大腿筋膜張筋に侵襲が加わりますので,股関節外転筋群の筋力低下にも留意する必要があります.
骨折の機能解剖学的運動療法 その基礎から臨床まで 体幹・下肢
今回は大腿骨骨幹部骨折例における理学療法評価についてご紹介いたしました.
評価項目を考える際には大腿骨骨幹部骨折例に対する手術療法の特徴を把握することが重要です.
また大腿骨骨幹部骨折は高エネルギー外傷が多いので,骨折の影響のみならず受傷時の軟部組織損傷にも留意する必要があり,X線や視診・触診によってどの軟部組織に損傷が加わっているかを評価することが重要となります.



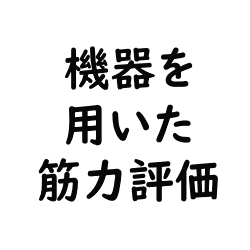

コメント